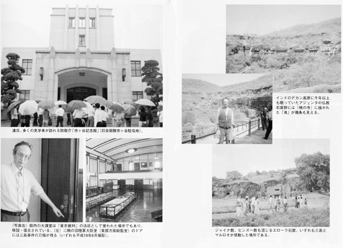
プロローグ
三島由紀夫の現場に立つ
市ヶ谷台の現場はいま
昭和四十五年十一月二十五日、三島由紀夫は自ら組織した私兵「楯の会」の四人と自衛隊を訪れ、益田東部方面総監を人質にとって自衛官らをバルコニー前広場に集めさせ、改憲を呼びかける檄を飛ばし、学生長の森田必勝とともに割腹自決した。
この壮大な劇は日本ばかりか、全世界に巨大地震並みの衝撃を与えた。
その余韻は日本ばかりかフランスでイタリアで、いや世界中で依然として燻り続ける。
いわゆる「三島事件」以後、左翼をのぞく日本人の間に活発な憲法改正論議を呼び起こし、論壇に保守主義への本格回帰の潮目をつくることにもなった。
日本人の心を激しく揺さぶった行動による三島由紀夫の問いかけは、時空を超え、精神的な波紋となって拡がり続けた。友人で世界的な作曲家だった黛敏郎は「精神的クーデター」と表現した。日本人の襟元をつかんで、激しく精神の覚醒を促した三島由紀夫の行動は、まさに『古今集』以来の「天地を動かす」行為だった。
三島の自刃によって日本国内の議論は左右両翼に豁然と分かれた。
三島を介錯後、自らも自刃して果てた楯の会学生長・森田必勝について、三島は命令書に「三島はともかく森田の名誉を恢弘せよ」と書いた。
森田は学生時代、筆者の親友の一人でもあった。私はすぐに三重県四日市の実兄宅に泊まり込んで日誌を抜粋し、ほかの資料も加えて森田必勝遺稿集を編集した。
四半世紀のちに畏友の中村彰彦が三年の取材をかけて足跡の分からぬままだった森田の関係者を訪ね歩き、世に問うた労作が『烈士と呼ばれる男』(文春文庫)である。
知られざる森田の物語がここに明らかにされ、また森田遺稿集もほとんどの研究書が爾後に引用し、第一級史料と評価が固まって復刻版がでた(『わが思想と行動』日新報道)。十年ほど前には森田の故郷、四日市市に慰霊碑が建立され、さらに数年前には森田を顕彰する銅像が建った。
それにしても三島の企図したものは何であったのか?
三島由紀夫の天皇論は文化概念としてのそれであり、基本は「お祭り」にあり、諸外国のキング、エンペラー、ツアーとはまったく異なって「祭祀王」(プリースト・キング)であると村松剛ら幾多の文芸評論家が指摘した。肯綮は『文化防衛論』『奔馬』や『憂国』などの作品に顕現されている。
三島は『日本文学小史』(講談社)で、近代化以後の日本文学はある意味ではつまらない、退屈なものだ、と明言し続けた。なによりも個人の思想感情の表現、あるいは個人が現に暮らす、周りの現実を写し取ることに焦点が絞られており、それが、いわゆる近代文学の成立であるけれども、ならばその後の日本文学はいかなる地平に到着したのか? 三島は「現実と個人を基軸としてそこに拡がる領域ばかりを果てしなく掘り返し続けてきたのである。とくに戦後派の作家達がそうで、不如意な現実と向き合い、そこに生きる個人の内側へと深くくぐり入りことをもっぱらとした」という意味のことを書いた。
そして戦後文学を三島は激越に批判した。
「個々の卑小な民俗現象の芥箱の底へ手を突っ込んで、ついには民族のひろく深い原体験をさぐりだそうという試みは、人間個々人の心の雑多なゴミ捨て場の底へ手を突っ込んで、普遍的な人間性の象徴符号を見つけ出そうという試みと、お互いによく似ている。こういうことが現代人の気に入るのである。マルクスとフロイトは、西欧の合理主義の二人の鬼子であって、一人は未来へ、一人は過去への、呪縛と悪魔払いを教えた点で、しかもそれを世にも合理的に見える方法で教えた点で、双璧をなすもの」(『日本文学小史』) 批判、罵倒の嵐が過ぎて
事件当時、日本の大手マスコミが三島由紀夫を犯罪者のごとく扱ったため、文壇・論壇の人々はなかなか積極的に三島評価に立ち上がらなかった。
三島をあしざまに罵倒したほうがマスコミの主流に乗れると計算高い評論家が大勢いた。
それでも林房雄、保田輿重郎、佐伯彰一、黛敏郎、藤島泰輔、山岡荘八、川内康範、北条誠ら四十数人が発起人となって、最初の三島追悼会を東京池袋で開催した。私も裏方の一人だったが、寒さをものともせずに一万人以上が結集した。昭和四十五年十二月十一日だった。
これが「憂国忌」の原型になった「三島由紀夫氏追悼の夕べ」である。
翌昭和四十六年二月には三島の思想と行動を通して日本を考えよう、との趣旨で三島由紀夫研究会の結成をみた。結成趣意書には「その祖国への愛と憂いを継承する」と謳われた。
爾来、毎月一回、日本を代表するあらかたの知識人、大学教授、文藝評論家、アーチストなどが三島を論じたり、想い出を語ったりの勉強会が「三島由紀夫研究会公開講座」と銘打たれ、三十五年間にわたって継続され、累計二百四十回を数えた。
毎年命日に開かれる「憂国忌」の母胎はこの三島研究会である。学生、青年に加え、OLや劇団員、市井の人々、とりわけ若い女性の参加も目立つようになった。墓前祭も年に一、二回は行なわれてきた。
昭和四十六年、憂国忌発起人に川端康成、小林秀雄らが引き受けると著名作家、文化人、俳優、実業家、評論家、大学教授ら三百名以上に発起人会はふくらみ、たとえば山岡荘八は「白き菊、捧げ祭らむ憂国忌」とする献句を届けてくれた。遠く海外からもサイデンステッカー、アイバン・モリスらから熱烈なメッセージが届いた。
かくして林房雄、林武、保田輿重郎、浅野晃、宇野精一、佐伯彰一、嘉悦庚人、竹本忠雄、小田村四郎らと「祭主」は交代しながらも、毎年毎年、十一月二十五日の命日には「憂国忌」は確実に開催されてきた。
誰に言われたわけではない。それでも日本をなんとかしようと地下から沸き出てくる清流水のように、ひとびとは集まり、自費を投じ、時間を割いて憂国忌を盛大に行なうことこそが三島・森田の荒ぶれた魂の安らぎになると信じてきたからである。
変化は静かに訪れた。
季語に「憂国忌」が加わった。内外の喧噪な批判をよそに二十五年祭には江藤淳、遠藤周作らも憂国忌発起人に加わり、文壇中心の国民的行事になった。最近は浅田次郎、中村彰彦、中西輝政、久世光彦、高橋克彦、立松和平、古川薫ら数十名が新たに発起人に加わった。
私自身の人生はこうして三島・森田追悼が中心になった。
いつしか三島の享年を越えて還暦を迎えた。五十歳のときに大病したあと、「共有したあの時代のことを記憶のある裡に書き残しておかねば」と『三島由紀夫蕫以後﨟』(並木書房)を書き上げ、ついで文学論『三島由紀夫はいかにして日本回帰したのか』(清流出版)を上梓した。
飯沼勲の自決現場にようやくたどり着いた
残る仕事は三島の作品の舞台をすべて訪ね歩く評論で個人的には三部作の完成となる。この小冊がそれである。
もちろん国内の著名な舞台はほとんどを歩いたが、最後まで分からなかったのは『奔馬』の主人公、飯沼勲の自決現場だった。
たとえフィクションの中の場所であるとはいえ、三島はどこかをモデルにしているはずである。
伊豆が好きだった三島の舞台設定から考えても候補地が多く、特定は難航した。なにしろ伊豆を舞台の三島作品といえば、『獣の戯れ』『禁色』『鏡子の家』『永すぎた春』「真夏の死」『剣』「苺」など。
ふとしたきっかけでモデルの現場を見つけだした人がおり、その話を聞くや伊豆の現場に向かった。
ほかにも有名な作品が夥しいが、『潮騒』『絹と明察』『宴のあと』『美しい星』『午後の曳航』などで作中に登場する現場はいまさら解説の必要はないであろう。
とはいえ『金閣寺』の舞台モデルで見落とした場所があった。
この小冊の最終取材で真夏の京都へ行った。ようやく脱稿寸前となって、「あ、まだ見落としている場所が四カ所ある」と気がつき、慌てて「そうだ、京都へ行こう」となった。歩くのがイヤになるほどの猛暑だった。
京都では大谷大学(金閣寺放火犯の溝口が通った大学)、建勲神社(ここで溝口は御みくじを引いて出奔先を決める)、妙心寺(金閣取材で三島由紀夫が滞在した御坊、筆者も当然ながらここに泊まった)、そして南禅寺(溝口が友人と遊山に出かける名刹)を廻った。
また『潮騒』のモデルとなった歌島(「神島」)へ行ったおり主人公の二人が裸で抱き合った観的哨の跡に立って、その描写が作品とそっくりであることに驚いたのは当然としても、遠く渥美半島の伊良子が見えたのは新発見だった。
作中にはわずか一行、「(歌島は)北には知多半島が迫り、東から北へ渥美半島が延びている」とさりげなく書かれているだけだが、私はこの海流の行き先を見つめながらフト徳川家康の蕫伊賀越え﨟を思い出すのだった。本能寺の変を知った家康は堺にあって服部半蔵を先頭に立て、凶変を避けて伊賀の山道を駆け、白子から船で伊良子へと逃れた。三島(平岡)家は代々徳川贔屓、新撰組局長の近藤勇慰霊祭に三島は花輪を供したほどの勤王左幕派の流れ。
ともかく現場に立ってみないと分からないその土地の匂い、風の音、風景の妙味、地元の人々の性格など新発見がある。
難題は海外の現場である。
生前、三島由紀夫は夥しい海外旅行(それも世界中)をしているが、作品に反映する顕著な場所にも行かなければなるまい。
そこで三十余年をかけて『暁の寺』の月光姫が登場するタイの薔薇宮、本多が衝撃を受けたインドのベナレス、同じく「又、会うぜ。きっと会う。滝の下で」と言った清顕の、その「滝」はいったいどこか? 大輪神社のそれか、インドのエローラ・アジャンタ遺跡の滝か、あるいは西伊豆・黄金岬の滝なのか、私は探し求めた。
『癩王のテラス』のアンコール・トム、『アポロの杯』に見えるギリシアのデルフィの神殿などへも時間ができると飛び出した。
三島がミュージカルに通ったニューヨークも、コクトーと会ったパリにも、アントニウス像に憧れたローマのバチカンにも……。
それらの印象などをあちこちに分載してきた。ようやくここに一冊にまとめて上梓に漕ぎ着けた喜びは筆では表せないものがある。
なお文中の敬称は引用文以外すべてを省略した。作品名の表記において『 』は単行本があるもの、「 」は論文か、小説短編でも、それ自体の単行本がなくて別の単行本、作品集もしくは全集に収録された作品であることを区別している。加えて年号は国内をあつかう記事は元号で、国際的な場面では西暦を用い、日本と海外にまたがる場合は併用とした。
三十六回目の憂国忌を前に平成十八年秋
筆者識
 目 次
目 次